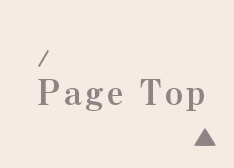CAD/CAM冠とは? その①CAD編
2020年04月23日
CAD/CAM冠とは? その①CAD編 先日のブログでCAD/CAM冠について簡単にご紹介させていただきました。 CADとはComputer-Aided Design の頭文字をとったものです […]


2020年04月23日
CAD/CAM冠とは? その①CAD編 先日のブログでCAD/CAM冠について簡単にご紹介させていただきました。 CADとはComputer-Aided Design の頭文字をとったものです […]
2020年04月18日
クリンチェック解説④ 25歳女性のケースです。 本ケースで矯正終了時の口腔内写真もご提示します。 主訴は上下の前歯の叢生(ガタガタ)です。 術前の口腔内写真です。 […]
2020年04月18日
続・保険で白い歯できる? 前回は健康保険適応で可能な直接法での白い歯の治療を解説しました。 今回は間接法により保険でできる白い歯に関して解説します。 間接法とはいわゆる型取りを行い、作業用の模型を作成し修復物を作成します […]
矯正治療に関する無料オンライン相談を設けています。治療の強要などは致しませんので安心してご相談ください。